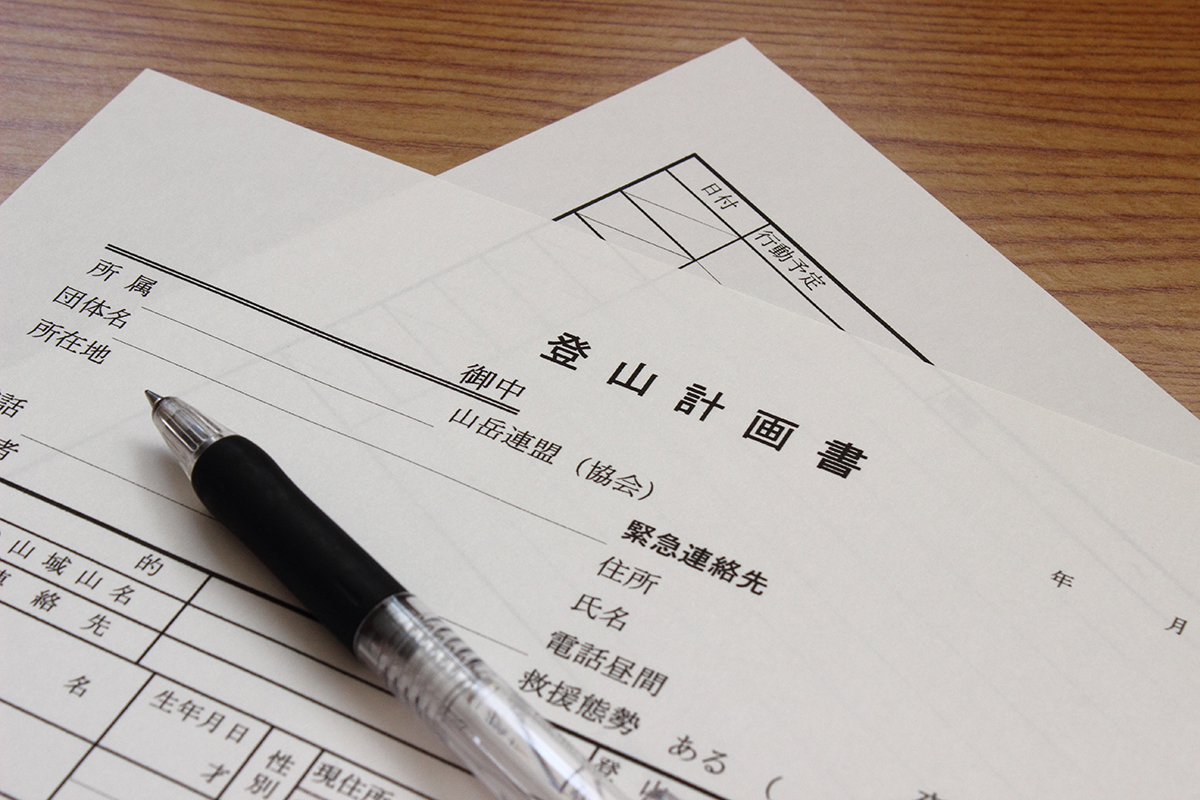バックカントリーで自然風景を見たり、感じたりしながら滑る体験は、多くの感動を与えてくれます。その反面、遭難や雪崩などのリスクもあり、相次ぐ事故のニュースが報じられています。そこで誤解されがちなのが、「スキー場の立ち入り禁止エリア」が「バックカントリーエリア」だという誤った認識です。この2つはまったくの別なエリアなのですが、ときおり混同しているような内容の報道も見受けられます。
バックカントリーをそのまま訳すと「裏山」となり、言うなれば、限りない自然がすべてバックカントリーというフィールドといえるでしょう。これに対して、滑走コースが整備され、きちんと安全管理されている区域がスキー場です。この2つの区域が具体的にどう違うのか、「全国スキー安全対策協会(一般財団日本鋼索交通協会)」の事務局長にお話を伺いました。
※2023/04/03取材時の内容を再掲載しております
バックカントリーエリアはスキー場の管理下にない
『全国スキー安全対策協議会』は、スキー関係の団体が安全性を高める方法を話し合うための組織です。どんなことをしているのかというと、全国のスキー場の標識や表示マークを統一したり、スキー場での行動規則やスノースポーツの安全基準を制定したりといった活動です。本来は“スキー場が管理するエリア”を対象に安全対策を発信し、注意喚起をしています。ですが、スキー場から管理区域の外に出てその先の雪山でバックカントリースキー・スノーボードをするケースが多いため、バックカントリー愛好者に対する注意喚起の必要性にも迫られています。
「まず、バックカントリーで滑るフィールドにはスキー場のようにパトロールがいないことを理解してほしいです。コース内でスキーやスノーボードを楽しむエリアは、安全対策がされているスキー場が管理している区域です。このエリア内で起こった事故はスキー場のパトロールが救助に向かいます。一方、バックカントリーの滑走エリアはスキー場がいっさい管理していない“雪山登山”の領域です。このエリアで事故や遭難が起こった場合は警察に救助要請します」(事務局長談。以下カッコ内は同)
つまり、スノースポーツ安全基準に沿った安全管理がされた区域で自己責任と自己の判断でスキーやスノーボードを楽しめるのがスキー場、安全管理されていない区域で自己責任と自己の判断で楽しむのが自然の雪山を滑るバックカントリーということ。それが各区域の大きな違いといえるでしょう。バックカントリーで事故が起こったとき、場所を分かりやすくするためなのかスキー場名が報じられることがあります。でも実際に事故が起こっている場所は、スキー場ではなく自然の雪山の中なのです。
そもそもバックカントリーエリアはどんな場所なのか
バックカントリーエリアとはどんなフィールドなのか、なぜスキー場と管理が違うのか。もう少し詳しく説明してもらいます。
「例えば、スキー場が管理している区域の外が国有林なら、そこは国が所有する土地であり国民の共有財産となります。スキー場の権限がおよぶ場所ではないので、スキー場サイドが『入ってはダメ』などとは言えないのです。こうした国民の共有財産区は、誰でも入っていけるわけで、きちんと自らのために入山の手順(登山届や装備など)を踏んでいれば、バックカントリースキー・スノーボードを楽しむことができます。だから、バックカントリーは決して禁止されたエリアを滑走しているわけではないのです」
スキー場とバックカントリーのエリアを説明するとき、『スキー場管理区域内』と『スキー場管理区域外』という言葉が使われます。文字だけ見るとどんなフィールドなのかイメージしにくいため、バックカントリーがスキー場内の『滑走禁止エリア』だと勘違いされてしまうのかもしれません。バックカントリーは国などが所有する『山の中』だとわかれば、スキー場とはまったく別のエリアであることや、禁じられた場所を滑っているわけではないことが理解できると思います。
どこまでがスキー場が管理している区域なのか
では、どこまでがスキー場の管理区域なのか。スキー場では境目がわかるように看板の設置などさまざまな対策をしています。
「スキー場ではもうずいぶん前から、「このエリアまでがスキー場』『この先は管理区域の外』とわかるようにしています。とくにバックカントリーが盛んな山域の場合、管理区域境界線が分かるように、スキー場のMAPとスキーフィールドに看板を立てたりして、その先がスキー場の管理区域外であることが分かるようにしています」
また、スキー場のWeb サイト内にスキー場利用の約款(やっかん)を載せ、注意事項や禁止事項などの告知もしています。
「約款とは、お客様とスキー場側との約束事ですね。こういうことはしてはいけないとか、注意してくださいねということが書かれています。その中に、注意事項や禁止事項を無視した場合は損害賠償の費用を請求しますよ、ということも載っています」
こういった約款があることはあまり知られていません。スキー場ごとに約款が用意されているので、どんなことが禁じられていて注意すべきことは何なのか確認しておくとよいでしょう。
スキー場の『立ち入り(滑走)禁止エリア』とバックカントリーエリアは別物
近年のスキー場は、スキー場敷地内の森を滑れるツリーランエリアを用意するところが増えています。スキー場の管理下にある森を開放し、滑走が許されているエリアです。ただし、滑走に適さないと判断した場所やコースに危険を及ぼしたり、その場所が地形的に危険な箇所は『立ち入り禁止エリア』『滑走禁止エリア』として侵入できないようにしています。スキー場の『立ち入り(滑走)禁止エリア』に入るのは『コース外滑走』と呼ばれる違反ルールです。
バックカントリーの事故が報じられると、こうした『立ち入り(滑走)禁止エリア』に侵入して事故が起こったものと勘違いされがちです。何度もいうようにバックカントリーエリアはスキー場の管理下にない山岳地帯であり、まったく別のエリアです。
登山届の重要性
登山届は、基本的に遭難や事故などの有事の際に利用するためのものですので、バックカントリースキー・スノーボードをするために山に入る際は、WEBや専用サイトを通じて『登山届』を提出することが推奨されています。
登山届が都道府県や地区の条例によって条例化されているところもありますので、行く山域によっては、提出しない場合は、条例違反等になる恐れもありますので、よく調べなくてはいけません。
近年は、スキー場のゴンドラやリフトを利用してバックカントリーに向かうケースが多々あるため、スキー場内に登山届の提出ポストが設置されていたり、提出先が掲示されている場合がありますので、それらを利用するのも方法です。
『登山届』には、日時やメンバー、行動予定、装備内容などを記入します。
これらの記入は、有事の際の捜索側にとって、とても重要な情報となり、捜索範囲や捜索日程にも影響を与えますので、正確に記入する必要があります。
もし何かしらの理由で行動ルートを変える可能性が想定されるのであれば、そのことも非常時の行動として登山届に記入しておくことが迅速な捜索・救助に結びつきます。
あくまでも登山届は条例で定められているエリア以外は、義務でなく任意となりますが、自分自身や家族のためにも徹底したい事項の一つとなります。さらに、提出先は前述した場所にプラスして、家族と自家用車のダッシュボードの上においておくことで、有用な情報となりえることがあるのです。
スキー場サイドが管理区域外で救助活動をすると費用はどうなる?
スキー場内ならパトロールに、バックカントリーエリアなら警察に救助要請をすると説明しました。ですが、バックカントリーエリアで事故があったとき、警察からスキー場に救助応援の要請が入るというケースがあります。この場合の救助活動では捜索費用が発生します。
バックカントリーエリアはスキー場の管理外であるため、公的機関から民間機関に対して救助応援の要請がくるかたちになるからです。
「スキー場サイドでは人員を割いたりスノーモービルを出したりするのですが、遭難の捜索は夕方から夜に行なうことが多いので、ナイター照明をつけるとその電気代に大変な費用がかかります。そういった費用の負担を請求させていだだくかたちになります」
こうした費用は遭難された方や、当人が亡くなられた場合は家族に請求がいきます。また、捜索が打ち切りになった後、家族などが民間の捜索隊に捜索要請することもありますが、これも有償になります。
「そういった多額の捜索費用をカバーしてくれる山岳保険に入っておくことも大切です」と、事務局長は山岳保険の重要性を伝えます。自己責任のもと自然の山の中を滑るバックカントリーではさまざまなことへの備えが大切。山岳保険への加入もそのひとつといえるでしょう。
バックカントリーではガイドと同行を
これまで説明してきたように、バックカントリーエリアはスキー場の延長ではなく、山岳エリアで滑る雪山登山の領域です。目的はどうあれ、スキー場の管理区域の外に出た時点で、そこは“山岳エリア”となります。
「バックカントリーエリアのような自然のフィールドを滑る方のほとんどは、そこがどんな環境なのか理解し、深い雪や自然地形の醍醐味を楽しんでいるのだと思います。ですが、雪山の知識や経験がない方が興味本位で立ち入ると、雪庇の下など雪崩がおきやすい場所を滑ったり、沢などに迷いこんで遭難したりするリスクがあります。また、自分が雪崩を起こすきっかけをつくってしまうということも認識しておいてほしい注意点です」
道なき雪上を歩いたり滑ったりするバックカントリーでは、地形の知識も必要ですし、雪の性質、気象、用具など、さまざまな知識や装備が必須です。事務局長は、「だからこそ、バックカントリーに出かける際はガイドと同行してほしい」と、ガイドの案内やガイド付きツアーへの参加を強くすすめています。
どうやってガイドを探せばいいかわからないという方は、例えば、「ニセコ・バックカントリーガイド」など行きたい山域でネット検索してみるのもいいでしょう」
自然そのままの山を滑るスキー・スノーボードは、非日常を味わえる格別な体験でしょう。
ですが、安全管理されたスキー内でも非圧雪エリアでパウダーランを楽しんだり、開放された森でツリーランを体験したりとさまざまな滑りを体験できます。それぞれの区域の違いを認識し、ルールをしっかり守り、安全にスキー・スノーボードを楽しんでいただけるとうれしいです。