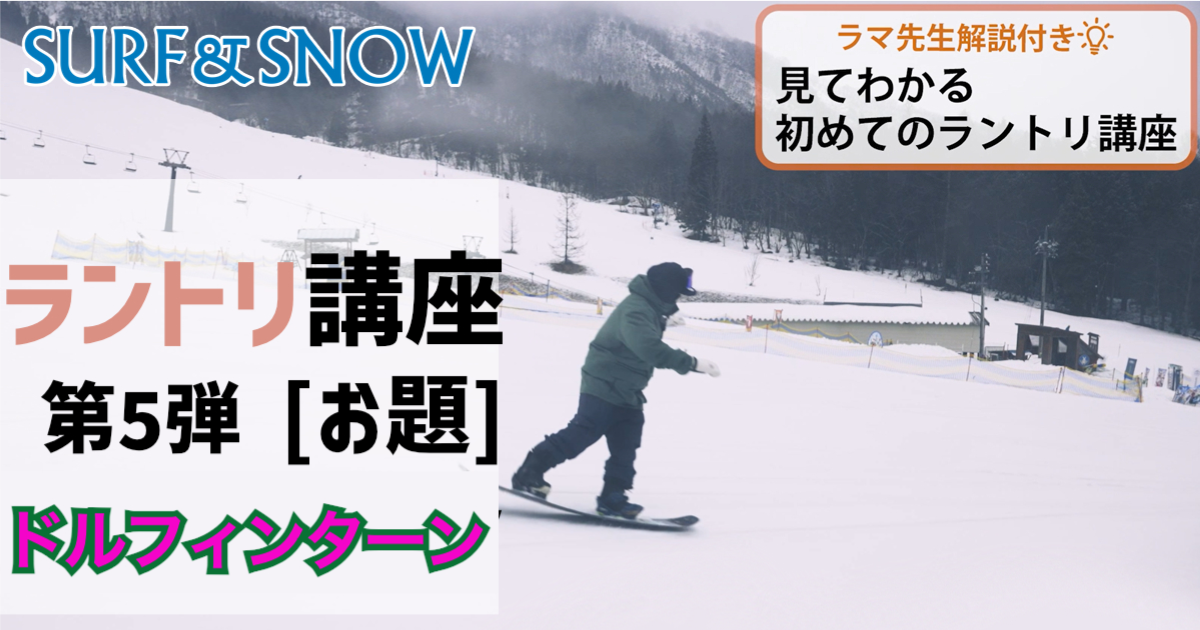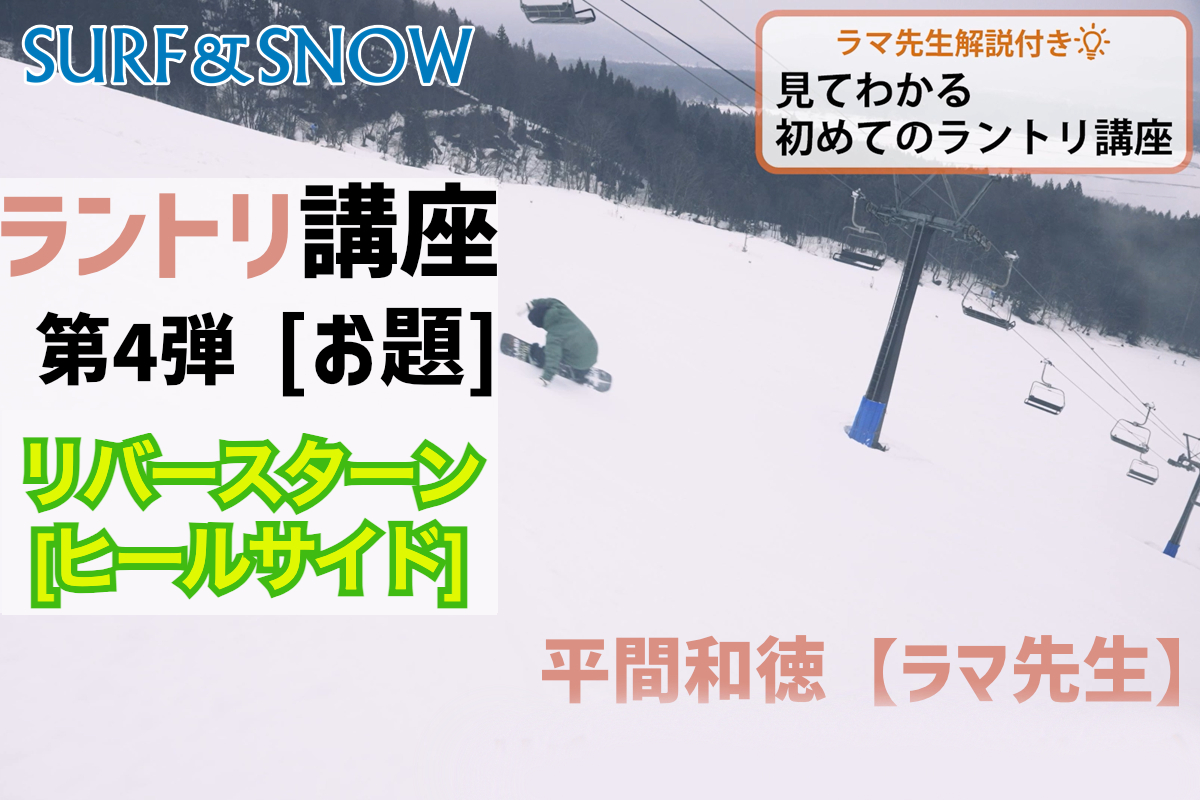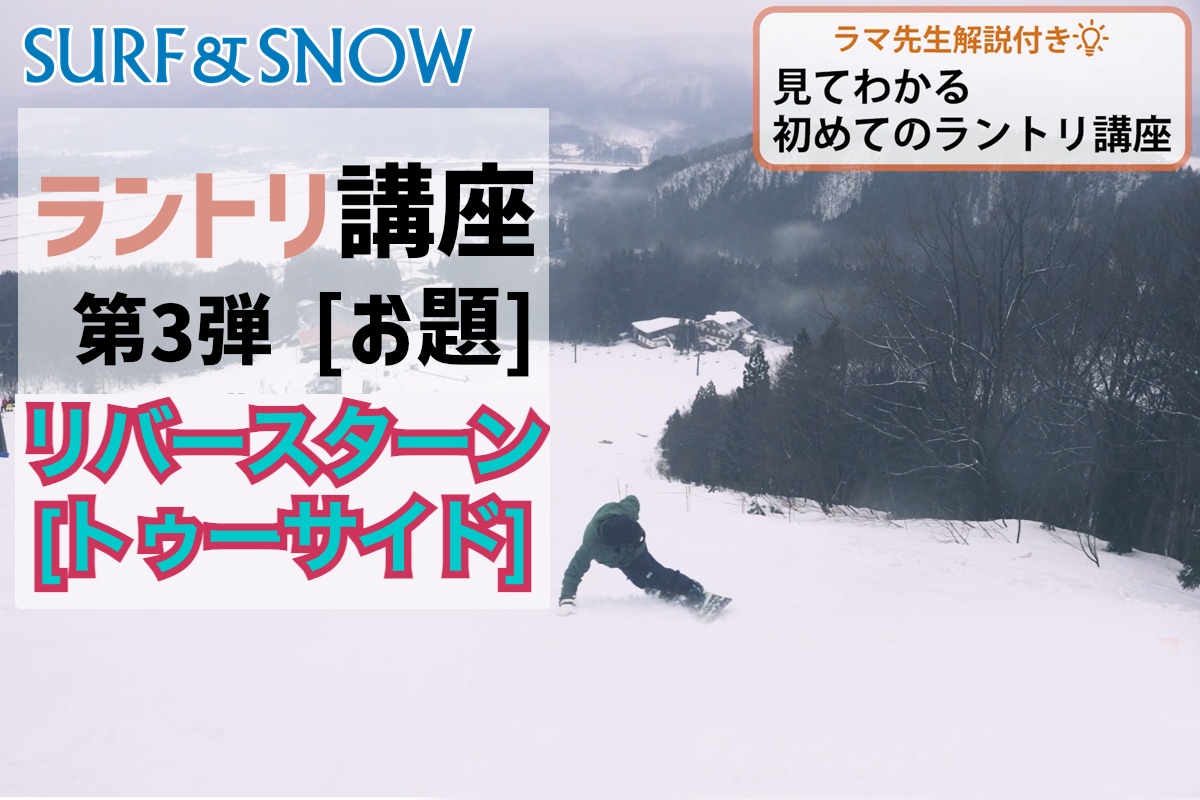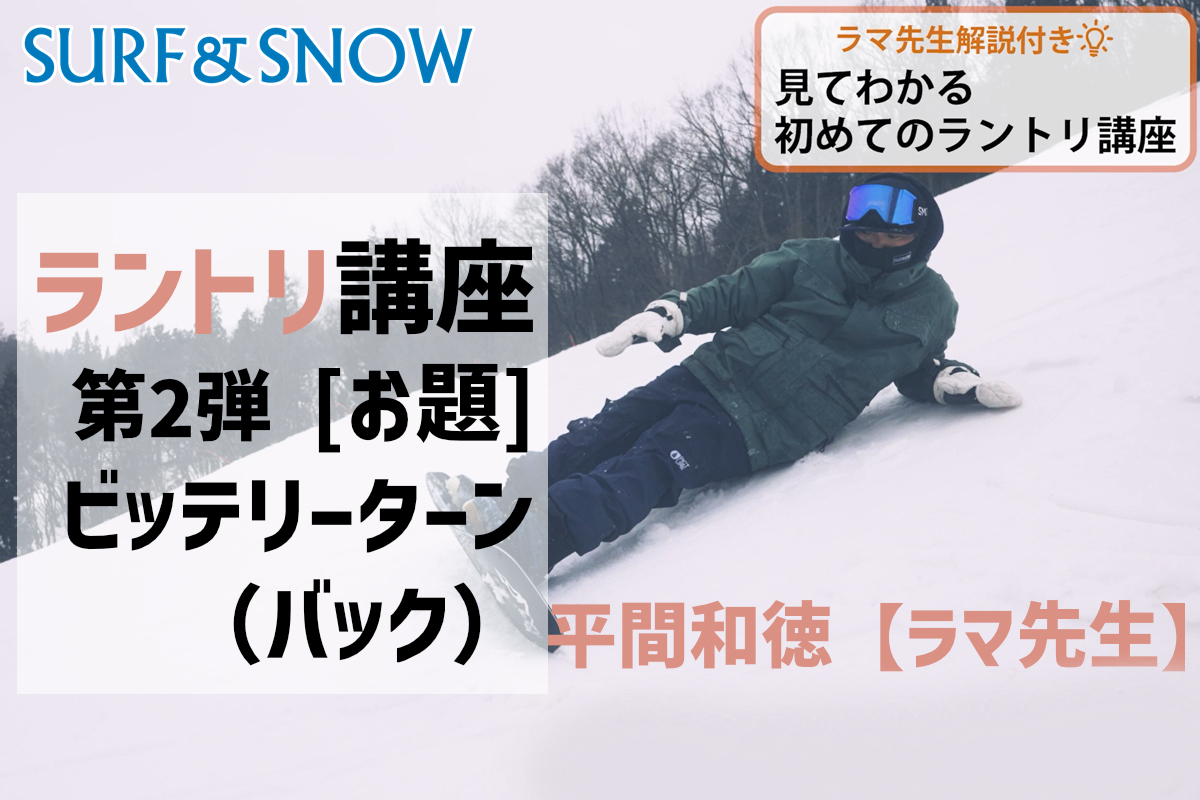スノーボードスクールは各スキー場で開校しています。まったくスノーボードをしたことがないビギナーから受け付けており、インストラクターの丁寧な指導のもと、用具の扱い方から滑りの基本まで、スムーズに上達できるレッスンを心がけてレッスンを行います。
ここでは、修学旅行生など多くの初心者を教えるレッスンで、インストラクター免許はなくても、それなりの滑走力があればインストラクターのアルバイトとして働いてもらうことはできるスクールもある。そんなとき、これが教えられれば大丈夫という12のTipsをご紹介。
【目次】初心者レッスンの流れ
<1> 先生の挨拶
<2> レッスンを始める前に
<3> 準備体操
<4> 転び方の練習
<5> ビンディングを付けてみよう
<6> スケーティングしてみよう
<7> スノーボードに慣れよう
<8> 片足だけ履いて、まっすぐ滑る
<9> スノーボードを両足で履いてみる
<10> サイドスリップを練習しよう
<11> 左右に移動してみよう。
<12> リフトに乗ってみよう。
<1> 先生の挨拶
写真提供:グランスノー奥伊吹
まずは、生徒とのコミュニケーションを行う為、挨拶から始めよう。この時に一人一人に目を配りながら、体調の悪い人や、不安な人の緊張を少しでも和らげよう。
<2> はじめる前に、生徒のブーツの締まり具合や、ウェアの着方、体調等を確認
初心者レッスンに参加するほとんどの人が、レンタルボードやブーツだったりと、道具に慣れていない人がほとんどです。道具が正しく使用されないと、ケガの原因となりますので、レッスンを始める前に、必ず一人一人の道具の状況を確認しましょう。
※持ち運びしやすい、ドライバーツール等を持っていると便利です
■ブーツがちゃんと履けているか。
初心者の方は、初めてスノーボードブーツを履きますので、普段の靴の様に履いてしまいます。ブーツによっては左右が分かりにくいタイプや、締め方が特殊なものもあるので、基本的な所から確認してください。
■インナーがちゃんとはまっているか(ねじれてたり、はみ出していないか)
初心者のほとんどが、スノーボードブーツのインナー(セパレートしたタンの部分)を中にしまう事を知りません。すでに締め終わっている人も面倒ですが、インナーの履き方まで見てあげてください。
■ブーツの紐が、ちゃんとしまっているか
初心者の多くは、インナー、アウター共に、締め方が甘いです。スノーボードのブーツは足首などを守る役目もありますので、インナー、アウター共に、しっかりと締めてあるか確認してください。
■ウェアパンツのパウダーガードが、ブーツの中に入っていないか。
初心者が間違えやすいナンバーワンが、ウェアパンツのパウダーガードをブーツの中にしまってしまう事です。上記写真(上)はNG例です。正しくは、上記写真(下)の様に、ブーツをカバーするようにしてください。こうしてあげる事で、転んだ時に雪の侵入を防げたり、風が入らない様になるので、防寒にもなりますので、正しくお伝えください。
■使用する板の長さは、合っているか。
レンタルショップや、友人に借りたりと、使う人に合っていないサイズで参加される方も多くいます。その人に合っていないサイズで練習すると、上達スピードが落ちてしまう事がありますので、楽しくレッスンを受けてもらうにも、事前に使う板のサイズが合っているか確認してください。
またこの時、レギュラーと(右利き・左足前) グーフィー(左利き・右足前)を確認し、間違っていれば、その場で直すか、手が空いているスタッフがいれば、セッティング調整をお願いしましょう。
■ビンディングの調整は大丈夫か(ベルトの長さ等)または壊れていないか。
いざビンディングを装着する際、固定するベルトの長さが足りずうまくつけられない事や、逆に長すぎてしっかりと固定されていない事が起きてしまいます。ビンディングは、板と足を繋ぐ大事な役割を担いますので、事前にベルトの長さや、ラチェット(固定調整金具)が正常に稼働するか、事前にしっかりと確認してください。
■グローブやゴーグル等、最低限必要なアクセサリーは持っているか。
寒い屋外でのレッスンとなるので、天候により必要になるアイテムが変わってくるが、基本的に必ず用意が必要な、グローブやゴーグル、ニット帽、理想を言えばヘルメットの準備があるか確認してください。例え晴れてる天候でも、ゴーグルをしていないと、目が長時間直接紫外線にさらされ、角膜の表面が傷つく雪目になってしまうので、注意喚起が必要ですので、下記リンクも確認してください。
■体調は問題ないか。
体調が悪い中、せっかくスキー場にきたからと言って、無理して運動をおこなう事は大変危険ですので、事前に生徒の体調を確認しておきましょう。
体調管理チェック項目。
1) 熱がある
2) 体がだるい
3) 吐き気がある、気分が悪い
4) 頭痛やめまいがする。
5) 顔や足にむくみがある。
6) 過労気味で体調が悪い
7) 睡眠不足で体調が悪い
8) 食欲がない
9) 疲れており、からだがだるい。
10) 二日酔いで体調が悪い
<3> 準備体操
寒さや緊張などで、体が固まっている状態で準備運動をせず、いきなり練習をはじめてしまうと、肉離れなどケガのリスクが高まります。特にスノーボードで痛めやすい、手首や足首、首回りは念入りに準備運動をさせてください。
<4> 転び方の練習
スノーボードは、両足が固定された状態で滑るので、前に転ぶ時は手をついてしまい、手首を痛めてしまう事が多く、反対に後ろ側に転ぶときは、頭を打ちやすくなり、大変危険です。ここでは、急な転倒の際、転び方を伝えます。
前に転ぶとき
胸側に転ぶときは、とくに手をつかないよう注意。転倒しそうになったら、すぐにヒジを曲げて両腕を胸の前で揃えます。そのままライディングするように転ぶのが安全な方法です。
★レッスンポイント
・転ぶときは両腕を曲げたまま体を丸め、衝撃を少なくします。
・ヒジを雪面につけるように上体を伸ばしてスライディング。
・ボードを引っ掛けないようヒザを曲げてボードを持ち上げます。
後ろに転ぶとき
お尻側に転ぶコツも覚えておきましょう。後ろに転倒すると後頭部を強打することがあります。頭を守るために、転倒しそうになったらすぐ後頭部を手で覆って保護します。
★ポイント
・ヒザを曲げて体を丸めて低い姿勢になり、衝撃を減らします。
・お尻、背中の順に雪面に体をつけます。
・背中が雪面に着いたら最後にボードを持ち上げましょう。
<5> ビンディングを付けてみよう
まずは、片足(レギュラーであれば、左足、グーフィーであれば右足)をビンディングにつけてもらいます。スノーボードではボードやブーツなど、履きなれないものを身につけます。いきなり滑らず、用具に慣れることからはじめましょう。まずは片足だけバインディングを装着し、ボードを履く感覚に慣れてもらいます。
<6> スケーティングしてみよう
スノーボードは雪上をするすると滑る特徴があります。まずは、片足だけボードを装着し、滑る動きに慣れてもらいましょう。ボードを履いていない後ろ側の足で雪面を蹴り出し、ボードを滑らせてみます。滑る動きに合わせてうまくバランスを取り、「ソール全体で雪の上を滑る」という感覚を体験。傾斜のない平らな場所を選んで練習しましょう。
<7> スノーボードに慣れよう
滑りの練習をするときや、リフト乗り場付近などで、ちょっとした傾斜を上ることがあります。片足にボードを履いた状態で傾斜を上がる方法を覚えてもらいます。ボードの向きや足運びなど、コツさえ覚えればスムーズに斜面を上れるようになります。
<8> 片足だけ履いて、まっすぐ滑る
はじめて傾斜で滑るときは、最初は片足だけ履いた状態で練習します。ゆるやかな斜面でトップを下に向け、そのままゆっくり滑ります。スピードの出にくい緩斜面で、滑り降りたら平地でスピードがおちて自然に止まるような地形が最適です。練習するときは、人通りの少ないゲレンデ下の緩斜面などを選びましょう。
※リフトから降りるときに役に立ちます
<9> スノーボードを両足で履いてみる
片足で滑る感覚に慣れたら、今度は両足にボードを装着してみましょう。その場でジャンプをしたり、ジャンプをして方向転換をする練習をして、両足が固定された状態に慣れていきます。
<10> サイドスリップを練習しよう
スノーボードの基本の滑りはサイドスリップ。ボードを横にして、エッジをずらしながら滑る方法です。エッジをつかったサイドスリップから練習してみましょう。
<11> 左右に移動してみよう。
木の葉落としとは、ボードを横にしたままで左右に移動しながら進む滑り方。ターンのように曲がるのではなく、同じ方向に体を向けたまま滑ります。木の葉落としができるようになると、滑れるコースのバリエーションが一気に増えます。
<12> リフトに乗ってみよう。
リフト下や初心者練習エリアで滑る練習を済ませ、ある程度滑れるようになったらリフトに乗ってコースで滑ります。はじめてリフトを利用するときは、乗り場や降り場で転倒するケースがよくあります。リフトに乗り降りする流れをイメージしてから、実際の利用をおすすめします。
「SCoach(スコーチ)は、スクールが働きたいインストラクターをレッスン単位で求人募集、応募して働くことができるスキマバイトサービスです。働きたい(レッスン)日を検索すると、求人募集のスクールとマッチングして、働いたその日に報酬(給与)を受け取ることができます。趣味や資格を生かして、自分に合ったスクールでスノーボードの楽しさを伝えよう。