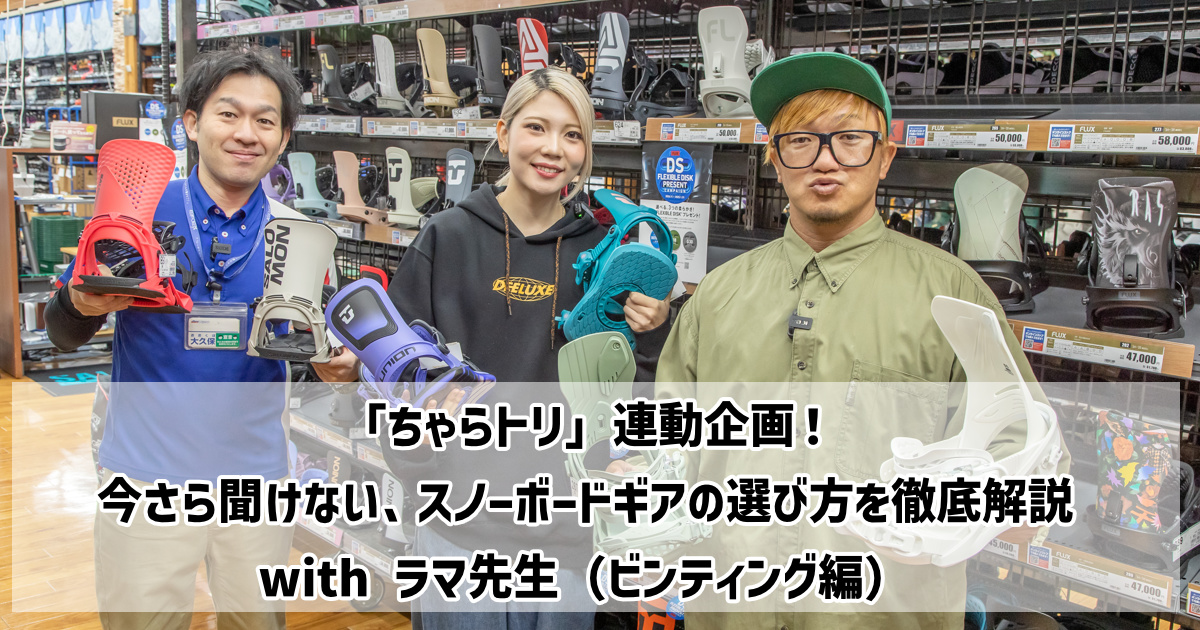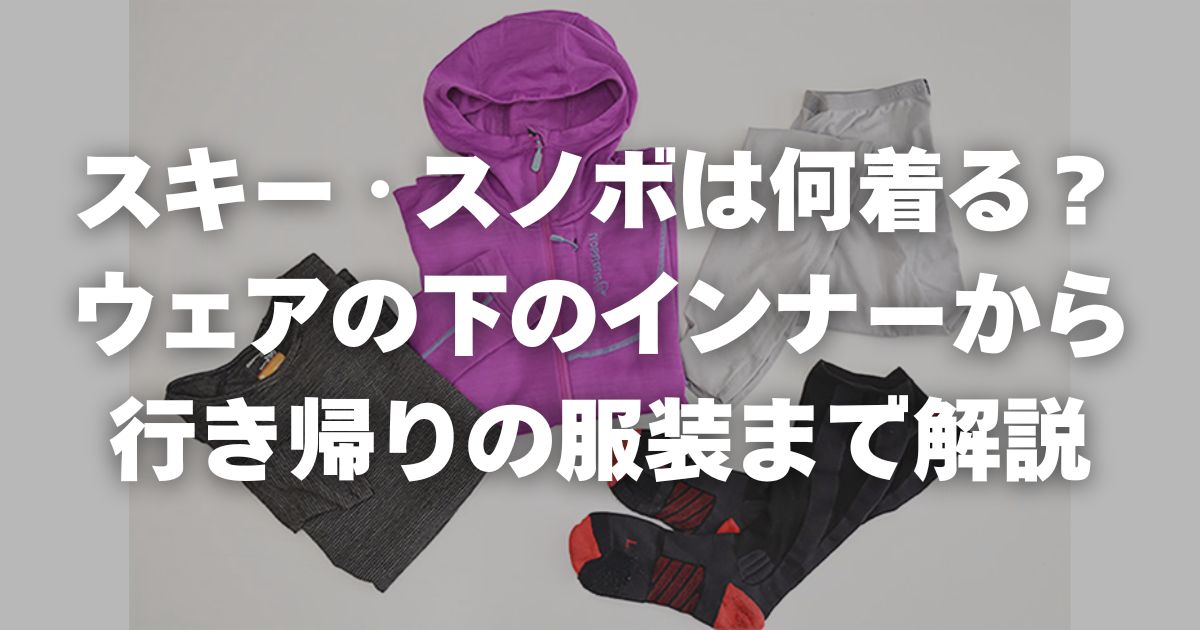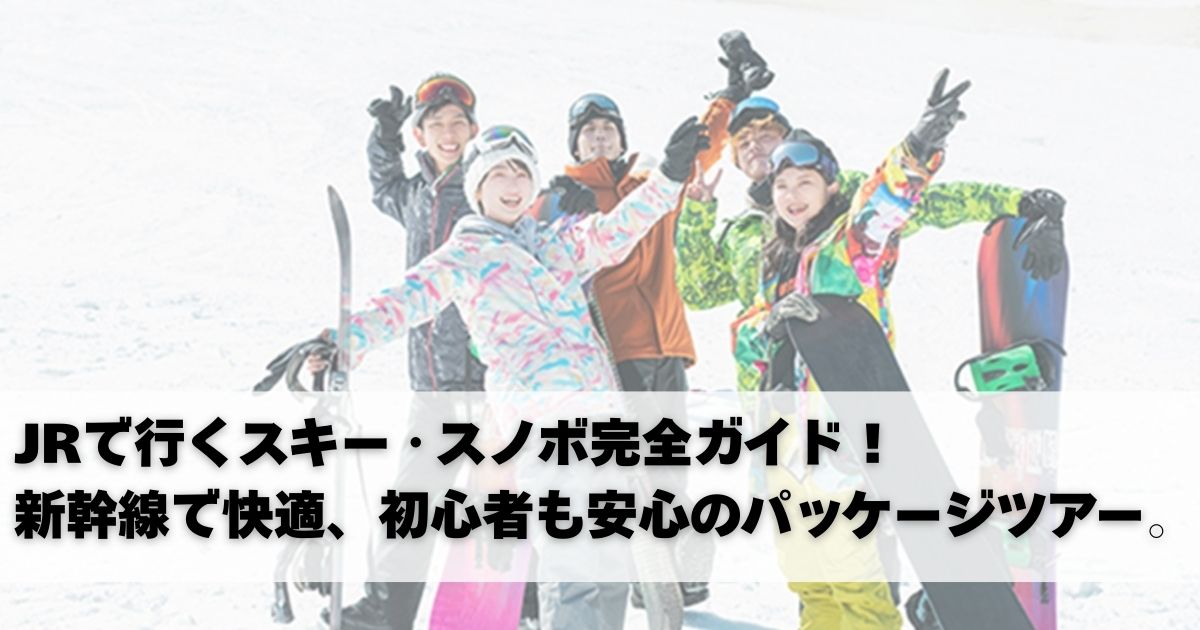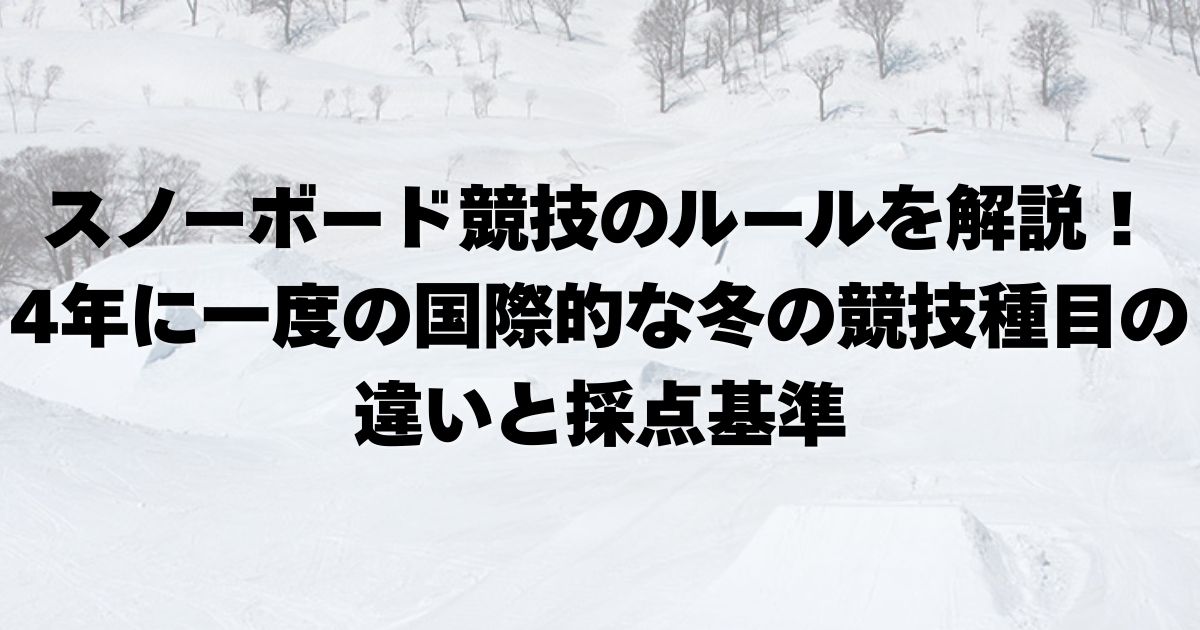自分にぴったりで自慢したくなるようなボードを選ぶにはどうしたらいい? そんな悩みを「ちゃらトリ」のラマ先生とインスタグラマーのiam SAKIががスーパースポーツゼビオで解決!失敗しないためのボード選びに必要なアレコレを丁寧に解説するので、じっくり目を通して頭に叩き込んでおこう!
![]()
平間和徳”ラマ先生”
通称「ラマ先生」として親しまれ、個性的なキャラが話題となり総フォロワー数が31万人を超える超人気プロスノーボーダー。全日本技術選手権を過去最多の5回制覇し、SAJスノーボードデモンストレーター(全日本スキー連盟、スノーボードインストラクターの指導)を長きにわたり務めた実力の持ち主。
![]()
iam SAKI
年間を通してスノーボードの滑走日数が80日以上という超アクティブ人気インスタグラマー。 釣り、キャンプ、ウェイクサーフィン、SUPなども楽しむアウトドア女子。
ギア購入店頭案内人はこちらの方⇓
![]()
大久保 兄さん
ゼビオ南長野高田店に勤務する、この道10数年のベテランSTAFF。自身もスポーツをこよなく愛し、プレーヤーとしても活動。特にスノーボードアイテムについて店内スタッフで右に出るものはいないスーパーアドバイザー。スポーツで大事な足回りのこだわりも強く、問題解決について頼れるお兄さん。
ボードって何を基準に選べばいいの?
ズラリと並んだ、たくさんのボードを前になにを基準に選んでいいのかわからないという人が多いだろう。まずは、ボードを特徴付ける、アウトライン、ソール形状、硬さによる違いを解説しよう。自分のやりたい滑りやライディングスタイルが明確ならばそれに合わせて、まだ定まってない場合はレベルに合わせてクセの少ないボードを選ぶようにするとよい。
シェイプによる違い
横並びになったボードをよく見てみると、パッと見でさまざまなシェイプがあることに気づく。ノーズの形状が丸いもの、カクカクしたもの、太いもの、またテールの形状も丸いものから尖っているもの、割れているものまで実にさまざま。またインサートホール(ビンディングの取り付け位置)の位置がセンター付近にあったり、テールに寄っていたり。大きく分けて、スノーボードにはディレクショナルとツインチップ、ディレクショナルツインの3タイプがある。
●ディレクショナル
ディレクショナルボードはノーズ・テールの形状が違い、ビンディングを取り付ける位置が真ん中よりテール寄りにセットされているモデル。ノーズが長く重心がやや後ろに設定されているので、進行方向への滑走性と安定性に優れ、ターンもしやすいため初心者やフリーランをメインとする人に◎
●ツインチップ
ツインチップボードは、ノーズとテールの形状がまったく同じで、ビンディングを付ける位置もど真ん中にセットされている。重心が真ん中に設定されているため、どちらのスタンスでも同じように滑ることができ、パークやグラトリなどのフリースタイル向けのボードとなる。スイッチで滑ることが多い場合にオススメだが、カービングやパウダーではややテールが長く感じることがある。
●ディレクショナルツイン
見た目はノーズ・テールが同じ形状をしたツインチップボードだが、重心をディレクショナルボードのようにややテール寄りに設定したボード。乗る位置だけでなく、ノーズよりもテールに硬さを持たせている場合もある。滑走性と安定性に優れながらスイッチでも扱いやすいので、フリーランもトリックも楽しみたい人に最適なオールラウンドボードといえる。
ソール形状の違い
見た目に分かるシェイプの違いだけでなく、ボードはソール形状にも多くの種類がある。ボードを平らな床の上に置いてみると理解しやすいのだが、ソール面のどこが“曲がっているか”によって分けることができる。各メーカーから出ているボードの構造は実に多様なのだが、ここでは基本的な人気の3タイプを紹介する。
●キャンバータイプ
10数年前までは、スノーボードのソール形状はキャンバー一択だったため、もっともクラシックなのがこのキャンバーボード。キャンバーとは、スノーボードを平らな面においたときに地面とボードの間にできる浮きの部分で、ボードの反り返りの隙間のこと。キャンバーがあることでボードを踏み込んだときのエッジングが安定し、ハイスピードでの安定性も◎となる。またキャンバーの遊びを利用すれば大きな反発力を得ることができるので、オーリー時に高さを出しやすい。初心者には逆エッジを受けやすいという面もあるが、スノーボードの基本動作しっかり覚えるには最適な構造といえる。
●ロッカータイプ
キャンバーとは逆に、ソールが船底のようにソール側へ膨らんだ形状がロッカー構造。接雪面が狭くて有効エッジも短くなり、エッジが引っかかることなくセンターを支点としてボードの回転性がよいので、ボードをズラしてルーズに乗ることができる。またパウダーで浮力が得やすいことも想像に容易だろう。遊びやすい反面エッジが抜けやすく不安定なのだが、このエッジングの甘さをカバーする工夫をエッジに凝らしたモデルがメーカーごとに登場している。より少ない力でターンもジャンプも行いやすく、逆エッジの可能性も少ないので、初心者にも扱いやすい。
●ダブルキャンバー
ボードセンターをロッカーに、両足下をキャンバーに設定したハイブリッド構造。ボードを真横から見たときに、アルファベットの「M」のような形状とになる。ロッカーのように取り回しやすく、足下に設定された2つのキャンバーが踏み込んだときのエッジングを効かせてターンのキレも実現する、キャンバーとロッカーのいいところどりといえる。グラトリがしやすく、逆エッジもしにくい。
●ハイブリットキャンバー
「ハイブリッドキャンバー」とは、ボードの中央部分はキャンバー形状になっており、ターンやエッジグリップ時に優れた安定性を提供し、ボードの前後(ノーズとテール)はロッカー形状になっており、パウダーや不整地での浮力が増し、ボードが簡単に浮きやすくなる特徴があり、ハイブリッドキャンバーは、これら2つの形状を組み合わせたものである。キャンバーとロッカーのいい所を掛け合わせた形状の板なので、いろいろな事にチャレンジしたい初心者には一番おススメとなる。
フレックスによる違い
ボードは形状だけでなく、モデルによりそれぞれフレックスが異なる。簡単にいうと、柔らかいボードと硬いボードがあるということ。一般的に、エントリー向けのボデルは柔らかく、上級者向けになるほど硬くなるといえる。ソフトフレックスのモデルは低速域で扱いやすく、ターンやトリックの練習もしやすい。一方ボードが硬くなるほど反応が速くなり高速域での安定感が出たり、反発がつよくパワフルなライディングを可能にする。
ボードを選ぶときには、ライディングスキルだけでなく、脚力や体重、ライディングスタイルも考慮して選ぶようにしよう。例えば脚力の弱い人や体重が軽い人が硬いボードに乗ると、しっかり踏み込めずにボードをコントロールしづらくなってしまう。また、グラトリやジブをメインに楽しみたいのであれば、硬めよりも柔らかめのボードのほうが扱いやすく、スタイルも出しやすいので、自分の目的に合わせて選ぶとGOOD。
サイズはどう選べばいいの?
スノーボードの長さは、身長、体重、スキルを考慮して選ぶ必要がある。一般的にはボードを床に立てた状態で、アゴから鼻の高さにくるものが長さ選びの基準となるが、初心者のうちは短め、慣れてきたらやや長めのチョイスでもOK。また身長だけでなく体重も重要で、体重が軽い人はやや短め、多い人はやや長めを選んだほうがベター。足が大きい人は、長さだけでなくボードのウエスト幅(センター幅)を気にする必要があるので、気になる人はショップスタッフに聞いてみるのが一番だ。
text:Makiko Kishino
▼本家動画はこちら▼【ちゃらトリ】 超重要ラマ先生ギア選びのコツ【FEET AXIS】
雪山応援ナビ
ウィンタースポーツを始めたいけど、始め方がわからない。行ってみたけど、心から楽しめなかった!という方達のために、最初のウィンタースポーツが楽しくなる環境づくりや、楽しいと感じられる準備のお手伝いをする特設サイト「雪山応援ナビ」。
![]()
今回の撮影協力店舗はこちら
<スーパースポーツゼビオ 長野南高田店>
住所
〒381-0034
長野県 長野市 大字高田1841-1
026-268-4811